活動レポート
平成29年6月16〜18日
第62回透析医学会学術集会・総会
平成28年9月17・18日
あいち県民健康祭り
平成27年9月19・20日
あいち県民健康祭り
平成26年9月14・15日
あいち県民健康祭り
平成25年9月14・15日
あいち県民健康祭り
平成24年9月12〜14日
第59回日本栄養改善学会学術集会総会
平成23年6月17〜19日
第56回(社)日本透析医学会学術集会・総会
|
|
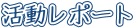
腎栄研として取り組んでいる種々の活動についてレポートを掲載しています。
第62回 日本透析医学会学術集会・総会 にて発表しました。
会期:平成29年6月16日(金) 〜18日(日)
場所:パシフィコ横浜(横浜市)
第62回 日本透析医学会学術集会・総会 にて、当会3グループより5題の発表を行いました。
発表内容(抄録より)
体重増加量と栄養素等摂取量・栄養状態との関連について【O-0606】
演者:○吉川妙子(白楊会病院)、今川智子(多治見第一病院)、井上啓子(至学館大学健康科学部栄養科学科 |
【目的】血液透析患者では、透析間の体重増加率や栄養状態が予後に大きく影響する。そこで体重増加率別に2群に分け栄養素等摂取量と栄養状態を比較した。
【対象・方法】対象は、尿量100ml/日以下で身体計測と食事調査が可能な246例。中2日の体重 増加率が5%以下(良好群)と5.1%以上(不良群)に分け身体計測値、血液検査、GNRI、nPCR、栄養素等摂取量と食品群摂取量を比較した。
【結果】良好群147例(男/76女/71)、不良群99例(男/55女/44)。BMI、%AC、%AMA、%TSF、%AMCは良好群が有意に高く、GNRI良好群95.3±5.4、不良群93.6±6.9であった。血液検査はnPCR、BUN、K、Piが不良群で有意に高値であった。摂取栄養量は、熱量(kcal/IBW)、炭水化物は不良群が有意に多かった。食塩摂取量は良好群0.13±0.03g/IBW
kg、不良群0.15±0.04g/IBW kgであった。食品別では、穀類、調理加工食品は不良群が有意に多かった。
【まとめ】良好群の食塩摂取量は有意に少なく、身体計測値、GNRIによる栄養状態は有意に良かった。 |
血液透析患者の1990年から5年ごとの栄養調査結果の報告【O-0614】
演者:東海腎臓病栄養食事研究会 ○清水和栄(白楊会病院) 井上啓子(至学館大学) 平賀恵子(新生会第一病院) 高橋恵理香(偕行会セントラルクリニック) |
【目的】血液透析患者の5年毎の栄養状態を調査し栄養評価を実施した。
【方法】東海腎臓病栄養食事研究会のメンバー施設の共同研究として、1990年から5年毎に通院血液透析患者を対象に3日間の食事調査と血液検査および身体計測を実施し栄養状態を把握してきた。
【結果】対象は、1990年204例、1995年395例、2000年408例、2005年317例、2010年449例、2015年342例である。5年毎の調査の比較では、年齢、ドライウェイト、BMIは有意に上昇し、身体計測値では%AC、TSF、%TSFに有意な上昇が見られた。また栄養素摂取量では、熱量はIBW当たり
32.2、30.3、29.2、28.6、29.4、29.0kcal、蛋白質はIBW当たり1.2、1.1、1.0、1.0、1.0gと有意な低下が見られた。その他の栄養素でもリンを除いて有意な低下が見られた。
食品群別摂取量では乳製品以外に有意な変化が見られ、特に穀類、油脂類、魚介類、果物の摂取量は年々に低下していた。これらの結果をさらに年代別に検討を加え報告する。
|
血液透析患者の血清リン値に及ぼす因子の検討【O-0630】
演者:○音川里美(さくら病院) 畠山圭吾(名古屋第二赤十字病院) 大瀧香織(岐阜ハートセンター) 平賀恵子(新生会第一病院) 井上啓子(至学館大学健康科学部栄養科学科) |
【目的】血液透析患者の血清リン値に影響する因子を検討した.
【方法】東海腎臓病栄養食事研究会会員施設に通う維持血液透析患者247例(年齢66.7±11.2歳、透析歴149±104ヶ月、血清リン値5.6±0.1mg/dL)を対象に3日間の食事摂取量調査、身体計測、血液生化学検査、服薬に関する問診を実施.血清リン値6.0mg/dLをcutoffとして群分けし、(1)内服忘れの有無と血清リン値の比較(χ2検定)、(2)内服忘れのない202例について、各項目との関連を調べた.
【結果】(1)内服忘れ無群は血清リン値が低く、内服忘れ有群は血清リン値が高かった(p=0.028).(2)血清リン値高値群において、透析前BUN・K値・nPCRが高く(p<0.05)、たんぱく質・脂質・リン・食塩・肉類摂取量が多かった(p<0.05).身体計測値・Kt/Vに有意差はみられなかった.
【考察】血清リン値を適正に保つには、服薬コンプライアンスを遵守した上で、食事からのリン摂取量を適切に管理することの重要性が改めて示唆された.
|
血液透析患者のNutritional Scores 別(PEWISRNM とGNRI)の予後予測能の比較【O-0992】
演者:○井上啓子(至学館大学健康科学部栄養科学科)、高橋宏(藤田保健衛生大学)、清水和栄(東海腎臓病栄養食事研究会)、伊藤恭彦(愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科) |
【目的】通院血液透析患者を5 年間追跡し,Nutritional Scores別(PEWISRNM I とGNRI)の予後予測能を検討した.
【方法】導入後6 ヵ月を経過した409 例の合併症,身体計測,血液検査,採血前3 日間の食事摂取量を調査し,ISRNM による区分にてPEW
を判定しGNRI を算出し,5 年間追跡した. 【結果】年齢64 ± 11 歳,透析歴8(3-14)年,BMI 21.1 ± 3.4kg/m2,Alb
3.7 ± 0.3 g/dL,栄養素摂取量,エネルギー30 ± 6kcal/kg,たんぱく質1.01 ± 0.22 g/kg であった.PEWISRNMは17.1
%で,GNRI 93.2 ± 5.6,92.2 未満は41.6 %であった.追跡期間の5 年間に101 例(24.7%)が死亡した.GNRI,PEWISRNM
ともに,有意な交絡因子を調整しても独立した予後予測因子であった.また,GNRI,PEWISRNM ともに予後予測能の改善に寄与していたが,両者の予後予測能はほぼ同等であった.
【結論】GNRI はPEWISRNM をよく反映し(AUC=0.810),そのCut-off 値92.2 で予後をよく層別化できた. |
家族構成別による栄養素等摂取量の比較【O-0996】
演者:○ 宇野千晴(すぎやま病院)、高橋恵理香(偕行会セントラルクリニック)、井上啓子(至学館大学) |
【目的】慢性疾患患者の食事指導を行う上で患者の生活環境・背景を知ることは重要である。それらの違いによる栄養素等摂取量や栄養状態を比較し栄養指導上の課題を明らかにする。
【方法】東海腎臓病栄養食事研究会の会員施設に通院する血液透析患者のうち調査協力が得られた342例(男性195例、女性147例、平均年齢67.14歳、透析歴9.5年)を対象に食事調査、身体計測、血液検査、透析基本項目を調査し性別、家族構成、調理担当者別に比較検討した。
【結果】家族構成は独居56例(男性38/女性18)、同世代と同居163例(男性92/女性71)、2世代94例(男性52/女性42)、3世代21名(男性9/女性12)、その他8名(男性4/女性4)であった。世代人数の増加に伴い熱量、たんぱく質摂取量をはじめ各栄養素摂取量が多く、また独居群の女性に基礎体重あたりの熱量、たんぱく質摂取量が多い傾向がみられた。
【考察/結論】栄養指導は、病状だけでなく家族環境も十分把握して行うことが大切と考えられた。 |
↑ページトップへ
あいち県民健康祭 にて愛知腎臓財団の活動に参加しました
開催日:平成28年9月17日(土) 〜18日(日)
場所:あいち健康の森(大府市)
今年度も、あいち県民祭りにて、愛知腎臓財団の塩分チェックコーナーのお手伝いをさせていただきました。
2日間で、会員16名が参加し、300件の集客がありました。
↑ページトップへ
あいち県民健康祭 にて愛知腎臓財団の活動に参加しました
開催日:平成27年9月19日(土) 〜20日(日)
場所:あいち健康の森(大府市)
今年度も、あいち県民祭りにて、愛知腎臓財団の塩分チェックコーナーのお手伝いをさせていただきました。
2日間で、会員15名が参加し、381件の集客がありました。
↑ページトップへ
あいち県民健康祭 にて愛知腎臓財団の活動に参加しました
開催日:平成26年9月14日(日) 〜15日(月)
場所:あいち健康の森(大府市)
今年度も、あいち県民祭りにて、愛知腎臓財団の塩分チェックコーナーのお手伝いをさせていただきました。
2日間で会員15名、非会員1名が参加し、349件の集客がありました。
↑ページトップへ
あいち県民健康祭 にて愛知腎臓財団の活動に参加しました
開催日:平成25年9月14日(土) 〜15日(日)
場所:あいち健康の森(大府市)
今年度も、あいち県民祭りにて、愛知腎臓財団の塩分チェックコーナーのお手伝いをさせていただきました。
2日間で会員16名が活動に参加しました。
↑ページトップへ
あいち県民健康祭 にて愛知腎臓財団の活動に参加しました
開催日:平成24年9月15日(土) 〜16日(日)
場所:あいち健康の森(大府市)
今年度も、あいち県民祭りにて、愛知腎臓財団の塩分チェックコーナーのお手伝いをさせていただきました。
参加された方は、2日間で411名でした。
今回の塩分チェックに参加されたことをきっかけに、日頃の食べている食事の食塩量や味付けに興味を持っていただける方が少しでも増えるといいな、と思います。

↑ページトップへ
第59回日本栄養改善学会学術集会 にて発表!!
会期:平成24年9月12日(水) 〜14日(金)
場所:名古屋国際会議場(名古屋市)
今年度の日本栄養改善学会にて、2題の発表を行いました。
(詳細は,下記参照)
発表内容(抄録より)
血液透析患者の食事摂取状況の変化 【03-222-114】
(発表者:白楊会病院 吉川妙子) |
【目的】東海腎臓病栄養食事研究会では、1990年より5年ごとに通院血液透析患者の栄養摂取量を含めた栄養状態を評価している。透析医療を取り巻く環境は、透析導入年齢の高齢化、糖尿病腎症の患者数の増加など変化している。そこで、栄養摂取状況では、各年代別の食べ方に違いがあるか、過去と比較し食品選択がどのように変化しているかなどを検討した。
【対象・方法】会員施設の通院血液透析患者で2010年は449例(男性252例・女性197例,平均年齢64.5±10.8歳)と、平均年齢である60歳代の患者2000年138名、2005年126名、2010年178名を対象とした。栄養状態についての調査は、採血前3日間の食事摂取量調査、身体計測、血液検査等を用い、統計解析はSPSSを使用した。
|
血液透析患者における血清リン値と食事摂取状況の関連性【03-222-115】
(発表者:さくら病院 音川里美) |
【目的】透析患者において血清リン値は生命予後因子の一つである。当会会員施設で血液透析を施行する449名に対し採血前3日間の食事摂取量調査・身体計測・血液生化学検査・透析関連指標の調査を行い、標準体重当たりのたんぱく質摂取量1.0g未満群・1.0〜1.2g群・1.2g以上群の3群に分け比較検討した所、たんぱく質摂取量の多い群においてリン摂取量が多く血清リン値も高い傾向がみられたが、リン摂取量と血清リン値に相関関係はみられなかった。そこで対象者を絞り更に検討を行った。
【方法】今回の調査においてたんぱく質摂取量が1.0〜1.2g/kgIBWであった147名(年齢64. 2±8.5歳、透析歴108.8±116.5ヶ月、男性58%)を、血清リン値6.0をカットオフとし2群に分け比較検討した。 |
↑ページトップへ
第56回(社)日本透析医学会学術集会・総会 にて発表!!
会期:平成23年6月17日(金) 〜19日(日)
場所:パシフィコ横浜(横浜市)
今年も日本透析医学会学術集会総会が開催されました。
大震災後の学会ということで,参加者も少ないのかと思いましたが,全国各地から大勢の方が参加され,会場は活気に溢れていました。なお,被災地からの報告が緊急企画として行われましたが,震災当日から現在へと続く現場の状況,被災された方や救援に向かった方々の心境に触れ,深く感じるものがありました。
この場をお借りして,お見舞いと,1日も早い復旧・復興をお祈りいたします。
さて,
腎栄研としては,「透析患者の5年毎の栄養評価」についての報告を1991年から継続しており*,今回で5回目の研究報告を行いました。(*前身の勉強会からの継続)
また,今年度は,腎栄研の活動についての報告も行い,合わせて2題の発表を行いました。
(詳細は,下記をご参照ください)
ところで,今回の学会が開催されている広い会場・たくさんの人の中で,「顔を知っているいつもの仲間達」に多く出会いました。お互いに声をかけ合い,講演や発表を聞いての意見交換を行なったり・・・。
会員の中には,それぞれの所属施設からの発表を行っている方もみえましたので,随分と心強かったのではないでしょうか。
腎栄研に所属し,栄養士同士の繋がりを とても有意義に感じた学会でした。
来年の開催地は北海道ですが,日頃の栄養管理・研究の成果の発表に行きましょう!!
発表内容(抄録より)
| 血液透析患者の5年ごとの栄養摂取状況と栄養状態 【P-5-253】 |
私たちは,1990年より5年ごとに通院血液透析患者の栄養状態を評価してきた。今回は栄養摂取量を含めた栄養状態の推移を中心に報告する。
【対象】1990年204例,1995年399例,2000年408例,2005年319例,2010年449例である。
【方法】透析関連基本調査,身体計測,血液データ,食事摂取量調査(採血前3日間の自己記録法)を実施した。
【結果】摂取熱量は,1990年 32±5 kcal,1995年 30±5 kcal,2000年 29±5 kcal,2005年 30±5 kcal,2010年 30±6 kcal,たんぱく質1990年 1.2±0.2 g/kg,1995年 1.1±0.2 g/kg,2000年からは 1.0±0.2 g/kgであり,1990年と2010年を比較すると熱量・たんぱく質ともに有意に低下していた。
この内,2005年と2010年の継続調査は95例で,5年間でDWや上腕筋囲長(AMC)などの身体計測値および血清アルブミン値(ALB)などが有意に低下(DW -1.2±3.0 kg,AMC -0.9±2.5 cm,ALB -0.2±0.3 g/dL)していた。一方,摂取栄養量は,熱量,たんぱく質ともに有意な変化は見られなかった。
|
| 東海腎臓病栄養食事研究会 発足から現在の活動報告 【P-5-255】 |
|
2009年11月、東海地区の栄養士および管理栄養士を対象とした腎疾患領域の会を発足した。目的としては腎と栄養に関する幅広い学習・研究を行うことで、東海地区の患者様への治療の一端を担う立場として、医療に貢献するという考えのもと、栄養士および管理栄養士の結束と質の向上を図ることにある。現在の活動は年2回の研修会と「CKDステージ2・3・5の栄養管理の研究」、「論文抄読会」、「血液透析患者の5年毎の栄養状態の評価」について、それぞれのグループに分かれて2ヶ月に1回のペースで研究会を開いている。発足から現在の活動状況、そして今後の課題、さらにはグループ活動を始めたことで出来上がりつつある栄養士間連携についての会員アンケート調査の結果も含め報告する。 |
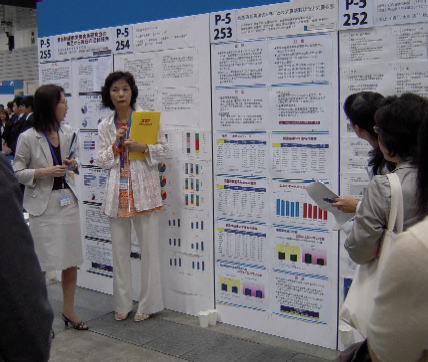 |
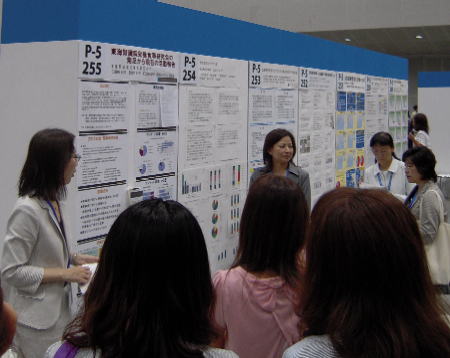 |
↑ページトップへ
文責:腎栄研 事務局
↑ページトップへ
ホームへ戻る
all copyright by 腎栄研
|
|